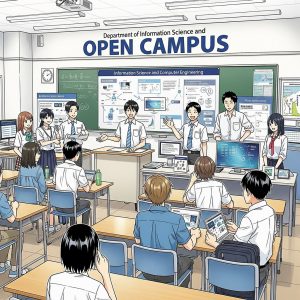麻谷研究室 4年生が卒業研究計画を発表! ~Aグループ発表会にて~
2025年8月1日(木)の3時限および4時限に、Aグループの卒業研究計画発表会が開催され、麻谷研究室の4年生8名がそれぞれの研究計画について発表を行いました。
今回の発表会は、Google Meetを使用したオンライン形式で実施され、学生たちは自宅や研究室から参加し、活発な質疑応答が交わされました。
発表された研究テーマは多岐にわたり、情報工学科らしい独創的で社会貢献性の高い内容が揃いました。以下に各発表テーマの概要をご紹介します。
- 「株価予測における深層学習モデルの比較」 川西 達也さんからは、株式投資が盛んになる中で、株価予測に用いられるLSTMとTransformerという深層学習モデルの精度と汎化性能を比較し、時系列予測能力の特性を明らかにすることを目的とした研究が発表されました。日経平均株価の終値データを用いてモデルの構築と性能比較を行い、投資戦略の精度向上に貢献することが期待されます。
- 「弾幕シューティングゲームにおけるAIの性能比較」 山下 健さんからは、AIを活用したゲーム分野に着目し、特に弾幕シューティングゲームにおいてAIを用いて最適なアルゴリズムを発見することを目指す研究が発表されました。OpenCVによるゲーム画面の二値化や、DQN、モンテカルロ木探索といったAIアルゴリズムを導入し、弾幕回避の性能比較を行うことで、将来的に弾幕STGへのAI自動操作実装の指針となることが期待されます。
- 「サイバーインシデント補足情報発信システムの開発 専門知識の無い層への低コスト支援を目指して」 鴨崎 多美子さんからは、サイバー攻撃による被害が顕在化する一方で、セキュリティ対策が未整備な中小企業が多い現状に対し、サイバーインシデントを専門知識のない人にも分かりやすく解説するシステムの開発が提案されました。MyJVN APIで脆弱性情報を取得し、ChatGPTで解説を生成、X(旧Twitter)で発信するシステムにより、中小企業の情報セキュリティ対策推進に貢献することが期待されます。
- 「問題を追加できる学習アプリケーションの開発」 田中 一世さんからは、スマートフォンの普及による手軽な学習の可能性に着目し、マイナーな検定試験など教材が少ない分野の学習者を対象に、ユーザーが問題文を入力できる学習アプリケーションの開発が発表されました。ノーコードツール「Adalo」を使用し、問題の作成・解答機能、訂正・削除機能、解答時間設定などを実装することで、教材の柔軟性に優れた学習環境の提供を目指します。
- 「ラーメン店に特化したLINE チャットボットの開発」 吉田 航さんからは、ラーメン店の情報が豊富にある中で、ユーザーの嗜好や状況に合った店舗を効率的に見つけるためのLINEチャットボットの開発が発表されました。LINE Messaging API、Google Maps API、食べログAPIを連携させ、ユーザーの入力に応じた最適なラーメン店を提案する機能に加え、過去の利用履歴に基づいたレコメンド機能の実装も目指し、ユーザーの利便性向上と地域飲食店の利用促進に貢献することが期待されます。
- 「DX化を促進させる体温管理 LINEBOT の開発」 菊池 巧巳さんからは、DX化が進む現代において、コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症対策として、日々の体温管理を効率的に行うLINE Botの開発が発表されました。LINEに体温を入力するだけでGoogleスプレッドシートに自動記録される機能や、熱がある場合に近くの病院の位置情報を取得する機能を実装し、個人・学校・職場での健康管理のDX推進に貢献することが期待されます。
- 「Whisper と ChatGPTを活用した高齢者記憶支援システムの開発」 金津 胡花さんからは、高齢化が進む日本において、軽度認知障害や認知症の患者増加に対応するため、AI音声認識技術を活用した記憶補助システムの開発が発表されました。Whisperで音声質問をテキスト化し、ChatGPTで応答を生成、Google Text-to-Speech APIで音声を返答するシステムを提案し、高齢者の記憶不安軽減と周りの人の負担軽減に寄与することが期待されます。
- 「SNS 投稿を対象とした日本語感情分析の精度と活用可能性の検討」 前本 拓さんからは、SNS上の日本語投稿から得られる感情や心理の分析に着目し、自然言語処理技術を用いた感情分析手法の精度と実用性を検討する研究が発表されました。2025年の参議院選挙に関するX(旧Twitter)投稿を対象に、BERTモデルを用いた感情分析を行い、その結果が社会的に有用な情報として活用可能かを評価することで、企業のマーケティングや行政の世論調査などへの応用可能性を探ります。
発表会では、学生たちは自身の研究テーマに対する熱意と深い理解を示し、教員や他の学生からの質問にも的確に答えていました。今回の発表で得られたフィードバックを活かし、今後の研究をさらに発展させていくことが期待されます。
麻谷研究室では、これからも情報工学分野における様々な課題に対し、積極的に研究に取り組んでまいります。